川崎市の葬儀でお悩みの方へ

口コミNo.1葬儀社が
疑問を解決!
地域貢献度
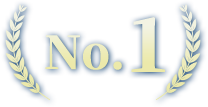
口コミ満足度
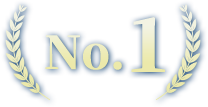
信頼と安心
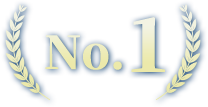
*日本経済リサーチ株式会社2022年2月期調査
川崎市の葬儀コラム|葬儀なら花葬
【目 次】
「不明瞭」な葬儀費用を適正化し
全て自社スタッフが行う葬儀社です
\ swipeスライドでもっとみる /
息子や娘も「この人なら大丈夫だよ」と言うくらい対応が…
続きを読む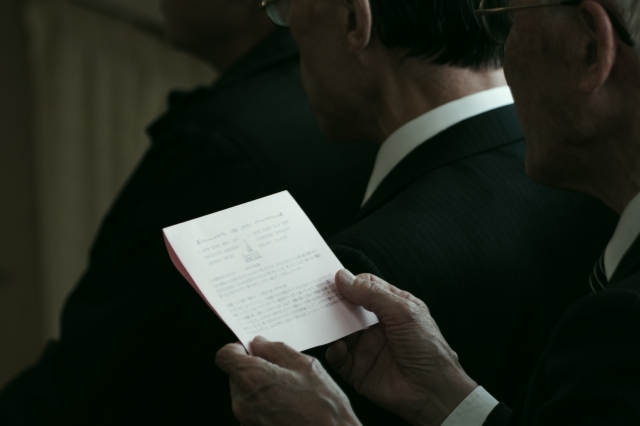
訃報とは誰かが亡くなったことの知らせを意味します。また、誰かが亡くなったことに加えて、いつ、どこで、葬儀を執り行うかなども伝えて、葬儀への参列を促す役割も果たします。あるいは最近では家族葬が多く、身内だけでの葬儀を行ったあとに訃報を流すこともあります。
では、訃報はどのような方法で流せばいいのでしょうか。この記事では、訃報の連絡方法とその内容についてご紹介いたします。
訃報では、故人が亡くなったという事実に加えて、次のようなことを同時に伝えます。
●通夜や葬儀の日時
●葬儀式場の場所
●喪主の名前と連絡先
このように、訃報は死の知らせだけでなく、葬儀をいつどこで行うかの連絡の役目も果たします。場合によっては、死因や宗派を伝えることもあります。
特に宗派に関しては、神式やキリスト教式など、独特な作法がある宗派での葬儀の場合は、訃報を通じて事前に伝えておく方が参列者に対して親切でしょう。
訃報は、死の知らせだけでなく、葬儀の日時を伝える役割があります。それは、悲しみの事実の知らせであり、同時に事務的な知らせでもあり、その両方を兼ねています。
ですから、電話でまず故人が亡くなったことを知らせ、そのあとにメールやFAXで葬儀の日時や場所を伝えるのがよいでしょう。
電話だけであれば、万が一日時や場所の言い間違いや聞きそびれがあった時に、参列者に対して大変な迷惑を与えてしまいます。
一方、メールやFAXなどの文字情報だけだと、逆に事務的すぎて、冷たい感じを与えてしまいます。
まずは電話、そして文字情報。この2段階の伝え方をおすすめします。
訃報を伝える範囲は、喪主がどこまでの人に来てほしいかによって異なります。
家族葬を例にとっても、家族だけで行うケースもあれば、家族以外に親戚も集まって行うケースもあれば、家族や親族以外にご近所の数名だけ、お世話になった人たちだけというスタイルもあります。
通常は次の順序で訃報を流します。
1.親族や近親者
2.親族以外で特にお世話になった友人や知人
3.故人の関係者(友人、知人、会社関係、学校関係、町内会、自治会など)
4.遺族の関係者(友人、知人、会社関係、学校関係、など)
もしも家族葬であれば、1または2になるでしょうし、一般葬のように広くご縁のあった人たちに参列してほしい場合は3や4にまで範囲は広がるでしょう。
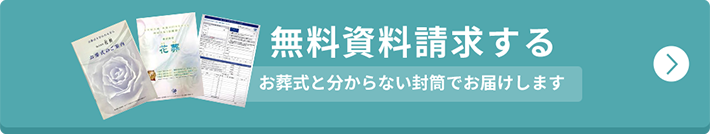
もしも葬儀の規模が大きくなりそうであれば、喪主がひとりひとりに声をかけるのは不可能です。その場合は、それぞれの方面の代表者に訃報を伝え、その人から拡散してもらうようにしましょう。
もしも町内の人に来ていただきたいのであれば、自治会長に声をかけます。会社関係であれば上司、取引先であれば担当営業マンや総務課などが窓口になるでしょう。
友人のグループがあれば、故人と一番近かった人に声をかけましょう。それぞれ代表の人が訃報を拡散してくれることでしょう。
最近では家族葬が増えていますが、家族葬の場合は事後報告もありえます。
家族葬の訃報は2つの方法があります。
故人の死を伝えた上で、弔問や香典は辞退する旨をきちんと伝えましょう。
中には「お線香だけでも」「御香典だけでも」という人も現れるので、その場合の対応方法はその状況によります。
家族葬は、訃報を伝えなければ相手には知られません。しかし、忌引き休暇を申請するためには学校や会社には伝えなければならないので、その時に家族葬で行う旨を伝えましょう。
事後報告として、葬儀を親族のみで執り行った旨と合わせて訃報を流します。
最近では年末の喪中はがきを受け取ってはじめて故人が亡くなったことを知るという人も多くいます。
中には「どうして知らせてくれなかったの」と苦言を呈す人もいるかもしれないため、故人の遺志や家族の意志であることをきちんと伝えましょう。
いかがでしたでしょうか?今回は訃報の連絡方法とその内容についてご紹介いたしました。ぜひ、ご参考にしてください。
訃報の連絡についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

㈱花葬は、現代表の大屋徹朗(※平成21年9月30日に「葬祭ディレクター1級」を取得)が、大手葬儀社の営業時代に感じた『もっと低価格でご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービスを提供したい』との思いから、2017年に川崎市中原区で創業した葬儀社です。2021年10月で創業5年目を迎えますが、2021年5月末現在、横浜市・川崎市で既に1.500件以上の葬儀提供実績があり、おかげ様で多数のメディアでも取り上げられております。
現在、川崎フロンターレの公式スポンサーを務めており、両者と地域貢献活動でも連携を取っております。その取り組みが評価され、2020年、2021年に社会貢献が川崎市より評価され、表彰を受けました。また、2021年より「SDG.S 川崎市ゴールドパートナー」としても認定されています。
弊社では、可能な限りお客様のご要望を叶えるための柔軟な葬儀プランと併せて、川崎市の公営斎場(かわさき南部斎苑、かわさき北部斎苑)と横浜市の公営斎場(横浜市戸塚斎場、横浜市久保山霊堂、横浜市南部斎場、浜市北部斎場)を利用することで、出来るだけ葬儀費用を安くするご提案を実施しております。
お陰様で、弊社はご利用いただいた皆様からの評価が非常に高く、「ご紹介」や「リピート」でのご依頼が半数を占めます。これからも『ご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービス』をモットーに、高品質な葬儀サービスのご提供に努めて参ります。
運営会社:株式会社花葬
川崎フロンターレ・川崎ブレイブサンダース 公式スポンサー
※表示価格は「資料請求割引適応後」の価格です。