
口コミNo.1葬儀社が
疑問を解決!
地域貢献度
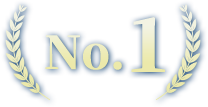
口コミ満足度
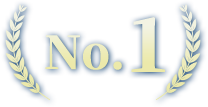
信頼と安心
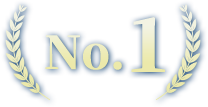
*日本経済リサーチ株式会社2022年2月期調査
川崎市の葬儀コラム|葬儀なら花葬
【目 次】
「不明瞭」な葬儀費用を適正化し
全て自社スタッフが行う葬儀社です
\ swipeスライドでもっとみる /
遺族の様々な要望に柔軟に対応する花葬はこれからも進化…
続きを読む
葬儀後の納骨式とは、故人様の遺骨をお墓や納骨堂に収める儀式のことです。
葬儀後の納骨の時期や準備はどうするのか、納骨にかかる費用や埋葬方法について詳しく解説します。
葬儀では故人様を火葬して遺骨を骨壺に納めます。葬儀後にこの遺骨をお墓や納骨堂に埋葬する儀式のことを納骨式といいます。
納骨式は、故人様の遺骨を納め、故人を偲びながら供養をする大切な儀式です。突然の逝去で、「納骨するお墓がない」「骨壺のまま身近においておきたい」など葬儀後に納骨で頭を悩ませている方もいらっしゃるでしょう。
葬儀後の納骨はいつ、どのように行うのか?納骨式の時期や納骨式の手順、遺骨の埋葬方法について解説していきます。是非参考にして下さい。
葬儀後の納骨の時期について、いつまでにやらなければならないという決まりはありません。葬儀が一段落して、葬儀後にご遺族が集まる四十九日法要などの時期に合わせて納骨式を行うのが一般的です。
仏教において四十九日は「故人様が極楽浄土にいけるかどうかを審判する日」という教えがあり、葬儀後にご遺族が集まって故人様が極楽浄土へ行けるように願いを込めてご供養をする日となります。
葬儀後、故人様の魂が現世から死後の世界へ旅立たれる日に合わせて納骨式を行うのが最もふさわしい日とされるのでしょう。
葬儀後四十九日法要に納骨をするお墓が用意できていない場合は、故人様が亡くなって100日後に行われる百箇日法要があります。この頃までにはお墓が準備できているので、葬儀後の百箇日法要の時期に合わせて納骨式を行う方も少なくありません。
葬儀後に故人様の遺骨を手元に置いておきたいと思うご遺族もいらっしゃいます。葬儀後に納骨する時期に決まりはありませんが、できるなら故人様の葬儀後三回忌までには納骨を行うようにしましょう。
葬儀後に納骨をしないと故人様の魂がいつまでも安らげる場所にたどり着けないとの仏教の教えもあります。故人様の魂は位牌に宿るとされています。葬儀後も故人様に傍にいてほしいならば手元に魂入れをした位牌をおきましょう。
葬儀後に遺骨の一部を自分の手元に置いて供養する「手元供養」という方法もあります。遺骨の大部分は納骨しますが、小さくした遺骨の一部をペンダントなどの中に入れていつでも身につけている方もいます。
遺骨の一部を手元に置く場合は法律上も問題なく、分骨すると故人様が成仏できないということもありません。仏教の開祖であるお釈迦様の遺骨(仏舎利)も世界各地に分骨されています。
葬儀後遺骨を自宅で管理する場合は、盗難や自然災害、火災などで遺骨を失ってしまうリスクも考えなれればなりません。
葬儀後の納骨式の時期が決まりましたら、納骨式の準備になります。納骨式の準備をするためのポイントを見ていきましょう。
納骨する場所として、先祖代々のお墓がある場合や故人様のお墓を新たに準備する場合は、そのお墓に納めればいいでしょう。
お墓を新たに準備するには、墓地となる霊園選びや墓石の種類・デザインの選定など完成するまで数ヶ月かかります。早めに準備することが必要です。葬儀後に一時的に遺骨を納骨堂に納め、お墓が完成次第遺骨を移しましょう。
近年は、核家族化が進み「お墓を建てても承継者がいない」「お墓は高額なので…」といった理由で、葬儀後に遺骨を納骨堂や樹木葬で納骨される方も増えています。承継者がいなくても、お寺や霊園が永代供養をしてくれるので安心できるのでしょう。
葬儀後にお墓以外への納骨方法を考えている場合は、事前にどのような方法で納骨するのがいいのかご遺族でよく相談されることです。
納骨の場所が決まったら納骨式の日程を決めましょう。葬儀後、故人様の三回忌までの法要のときに納骨式も併せて行うのが一般的です。
葬儀は友引を避ける方もいますが、納骨式に六曜は関係ありません。ご遺族で相談し納骨式の日程を調整します。
菩提寺があり、お墓もそのお寺にある場合はお寺に日程について事前に確認を取っておきましょう。納骨式には僧侶に読経もお願いします。土日や法要が多い時期は混雑しますので早めに僧侶の日程を確保する必要があります。
遺骨を納めるためのお墓がお寺でなく霊園などにある場合は、こちらにも連絡し予約をしておきます。埋葬許可証と墓地使用許可証を墓地の管理者に提出しておく必要があります。
葬儀後、故人様が墓地の名義になっていた場合は、納骨式までに墓地の名義変更をしておきましょう。納骨の予約時に名義変更の手続きに必要な書類や方法を確認しておけば手間が省けます。
納骨式でお墓のカロート(遺骨を納める場所)の入口を開閉するのに石材店などに来てもらう必要がある場合は事前に連絡しておきます。ご遺族だけで開閉ができる場合は問題ありません。
納骨式に間に合うように墓石に故人様の戒名・俗名・命日を石材店に彫刻してもらいます。早めに手配しておきましょう。
菩提寺がない場合や宗教・宗派を問わない場合、仏式で法要や納骨式を行いたいときは僧侶を派遣してもらえるサービスがあるので葬儀の際にお世話になった葬儀社に依頼するとスムーズに行きます。
特定の宗派の僧侶を指定することもできます。もちろん個人でも依頼でき、「僧侶派遣サービス」とインターネットで簡単に検索することができます。
僧侶派遣サービスの場合は、予約時に料金をクレジットカード決済ができます。納骨式当日僧侶に現金で払う場合は、白無地の封筒で大丈夫です。「お布施」の表書きは不要です。納骨式後にコンビニや金融機関からの後払いも可能です。
葬儀後にご遺族が一堂に会する法要・納骨式です。時間が許すのであれば納骨式終了の労いの場として会場・料理などの手配もしておきましょう。葬儀後に故人様の思い出をご遺族で語り合うのもご供養となります。
葬儀後の納骨式についての日程・場所が決まれば、参列してもらう親族や故人様の友人などに連絡します。お身内以外の参列者が多い納骨式であれば案内状を発送しましょう。
最近は、パソコンを使ってEXCELで作成した法要案内状を無料テンプレートで簡単に作成できます。
家族だけで納骨式を行う場合も、念のため親族や友人などに声を掛けておきます。納骨式に参列を希望していた方が納骨式の終了を知って後でトラブルになることを避けるためです。
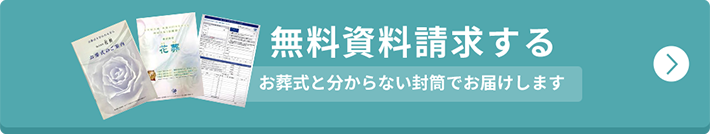
納骨式にかかる費用はどれくらいでしょう。葬儀後故人様を納めるお墓がすでにある場合として、納骨式での項目ごとに費用相場を見ていきましょう。
葬儀後の納骨式をお寺や霊園で行う場合は、お寺や僧侶への「お布施」として30,000円から50,000円程度が相場と言われています。
この他に、納骨式後に僧侶を会食の場にお呼びしたが辞退された場合は「御膳料」を、お寺から法要の場所まで一定距離がある場合は交通費として「御車代」を状況に応じて5,000円から10,000円程度を別包みでお渡しします。
僧侶派遣サービスの場合は35,000円~となっています。これ以外の料金は必要ありませんが、宗派を指定する場合は5,000円程度加算されるようです。
葬儀後に法要・納骨式に合わせて故人様の塔婆を作る場合はお寺に依頼します。塔婆とは故人様を供養するために、お墓の後ろに立てる戒名などが書かれた細長い木製の板のことです。1本2,000円から5,000円程度かかります。
葬儀後納骨式までに墓石へ新たに故人様の戒名などを彫刻してもらう場合、石材店に依頼します。彫刻料の相場は30,000円から50,000円程度かかります。
納骨する際にお墓のカロート(遺骨を入れる場所)の入口を開閉するために石材店に来てもらう必要がある場合、納骨作業費用として15,000円から30,000円程度かかります。
納骨式では祭壇に生花を飾ります。故人様の好きだった食べ物や飲み物、お線香やロウソクなども用意します。祭壇の形式やお花にもよりますが10,000円から20,000円程度はかかります。
法要を行う会場使用料が別に10,000円から30,000円程度かかる場合があります。お寺の本堂などで法要を行う場合は会場使用料はお布施に含まれます。
納骨式にかかる費用は8万円~18万円
納骨式にかかる費用としては大体80,000円程度から180,000程度が見込まれます。
葬儀後に法要と納骨式が同時に行われる場合、参列者はお香典を包んできます。香典の相場としては、故人様との関係によりますが5,000円から10,000円程度になります。
さらに参列者は法要・納骨式後に会食が行われる場合は、5,000円から10,000円程度上乗せして包むのがマナーとなっています。
法要・納骨式後の会食費は1人5,000円から10,000円程度かかります。会食後に、参列者が解散して帰宅する際に引き出物を手渡す場合、別途この費用もかかります。納骨式のお返しの相場は、3,000円から5,000円が一般的です。
一般的には施主がこれらの費用を負担します。参列される方も法要・納骨式にある程度のお香典を包まれてくるとしても、一時的にはかかった費用を誰がどのように負担するのか後でトラブルにならないように、ご遺族でよく相談しておきましょう。
葬儀後の納骨式に備えていろいろ準備してきました。納骨式当日に必要なものをチェックしておきましょう。
納骨式はお墓に遺骨を納める儀式です。当日故人様の遺骨の入った骨壺がなければ納骨式はできません。
骨壺をそのまま納める場合もありますが、納骨の形態によっては遺骨を骨壺から出して納骨袋や、専用の収骨容器(樹木葬などの場合)に粉骨して入れ替える場合があります。事前に確認しておきましょう。
故人様の遺影や位牌は納骨式に直接必要なものではありません。納骨式後の会食の場に故人様の遺影や位牌がテーブルの上にあると参列者も故人様を身近に感じ偲ぶことができます。
葬儀の際、火葬許可書に火葬場の捺印が押印された書類になります。遺骨を埋葬するために必ず必要な書類となります。埋葬許可証がないと死亡届を提出した市町村役場で再発行の手続きが必要です。
通常、埋葬許可証は紛失しないように故人様の遺骨の骨壺を納めてある白木の箱に一緒に保管されています。
遺骨埋葬許可書と同様に市町村役場が発行しているものです。納骨で霊園墓地を使用する場合に必要になり、墓地使用許可証を墓地の管理者に提出します。
墓地の管理者に無断で遺骨を納骨すると法律違反に問われることもあるので準備しておきましょう。
お墓を親族で共有している場合や先祖代々のお墓に納骨する場合はお墓の所有者から墓地使用許可証を借りて提出します。
祭壇に飾る生花を忘れずに手配しておきます。墓前におく故人様が好きだった菓子や食べ物、飲み物、嗜好品は準備しましたか。
宗派によって用意するものが異なる場合があります。わからない場合はお寺や霊園に問い合わせると教えてくれます。
そのほか納骨式で墓前に手を合わせるときには数珠やお線香、ロウソクなどが必要となります。必要なものは納骨式当日忘れないようまとめて用意しておくことです。
また、納骨式当日は会食をしない場合であっても参列者へのお茶やお菓子などは用意しておきましょう。お寺で法要・納骨式を行う場合はお寺側が準備してくれます。
納骨式の参列者に渡す引き出物も忘れてはいけません。納骨式に参列される方からは通常、「御仏前」や「御供」をいただきます。そのためのお返しの品を準備しましょう。
納骨式のお返しにはのし紙をつけるのが一般的です。のし紙の上側に「志」や「粗供養」として、下側に施主の名字を入れます。のし紙の水引の色は黒白か黄白を使い結び切りにします。
納骨式のお返しの相場は、3,000円から5,000円が一般的です。お返しの定番としてはお茶、海苔、調味料、そうめんなどの消え物やタオル、洗剤などの日用品が選ばれています。持ち帰る参列者のことを考えて軽くてかさばらないものを選びましょう。
最近は受け取った方が品物をカタログから選べる「カタログギフト」が人気となっています。
お布施については現金を包む紙袋を用意しましょう。僧侶に対する感謝の気持ちを形に表すのであれば、奉書紙を使って包みましょう。
お札はなるべく新札を用意しお札の向きは揃えておきます。相手が包みを開けたときに金額が確認しやすくなります。弔事には新札を包みませんがお布施は関係ありません。
水引は必要ありません。黒白や黄白の水引は、故人様を供養する意味合いがあります。仏事であってもお寺にはご不幸がないのでお布施には必要ありません。
奉書紙が用意できない場合は市販ののし袋でかまいませんが、水引の色は双銀か黄白で、結び方は淡路結びか結び切りを選びましょう。のし袋は文房具店やコンビニで買えます。
表書きは黒墨ですが筆ペンでかまいません。「お布施」以外に「御車料」や「御膳料」用のものも必要になる場合がありますので準備しておきましょう。
僧侶派遣サービスなどに依頼した場合は、利用料金を白無地の封筒に入れ表書きは書きません。
葬儀後に行う納骨式の流れを見てみましょう。納骨式の流れは宗教・宗派によって違いがありますが、仏式の一般的な流れで説明します。
納骨式当日には墓前や献花台など遺骨の埋葬地前にお供え物、供花や焼香台を並べて準備します。
準備が終わりましたら、納骨式の冒頭は、施主が遺族を代表して参列者に対しての感謝の挨拶から始まります。葬儀後のご遺族の近況や日頃のご厚誼に感謝を伝えます。
納骨後に会食を用意してある場合は挨拶の終わりに忘れずにご案内をしておきます。
挨拶の後は、故人様のご供養のために僧侶による読経を納骨する墓前や献花台前で行います。
読経が終わりましたら納骨となります。お墓の下のカロート(納骨室)の入口を開けて遺骨を納めます。カロートの入口の開閉はご遺族ができるタイプのものであれば問題ないですが、難しい場合は石材店に事前に連絡して当日開閉してもらいましょう。
カロートの入口を開けたら骨壺を収納します。関東地方では骨壺ごと遺骨を納めますが、関西地方では骨壺から遺骨を納骨袋に移して納めます。
納骨袋は市販されており素材は土に還る木綿や絹、麻など天然のものを使用しています。色の決まりはなく白が一般的ですが、故人様が好きだった色でもかまいません。ご遺族が故人様の着ていた着物で手作りの納骨袋を作成することもあります。
納骨の際遺骨の並べ方に決まりはありませんが、基本として古い遺骨を奥に、新しい遺骨は手前にするとされています。
カロートが遺骨で満杯になった場合は、古い遺骨から順に骨壺から出してカロート内に撒いたり、納骨袋に入れ替えたりする方法があります。ご先祖の遺骨と一緒に納骨して、土に還す地方もあります。
宗派により納骨の方法が異なる場合があります。事前にお寺や霊園に相談して確認しておきましょう。
納骨が終了すると2回目の読経を僧侶が行います。この読経は「納骨経」と呼ばれ、故人様の魂を供養するためのものです。この読経は墓前や献花台の前ではなくお寺に移動して本堂で行う場合もあります。
僧侶が納骨経の読経を始めたら参列者は焼香を行います。焼香を始めるタイミングは僧侶が指示してくれます。焼香の順番は施主、ご遺族、親族、友人・知人の順となります。
焼香までが納骨式とされ、参列者の数にもよりますが通常は1時間以内で終わります。僧侶がここで帰られる場合にはお布施を忘れずにお渡ししましょう。お布施は袱紗に包んでおき手渡しせずにたたんだ袱紗に乗せて渡すのがマナーです。
袱紗にはいろいろな色があります。紫色は慶事にも弔事にも使うことができるので一つあると重宝します。
僧侶が会食をご辞退された場合は「御膳料」、タクシーなどで帰られる場合は「御車料」を用意しておきましょう。
菩提寺がありお墓もお寺の墓地にある場合は、法要・納骨式が始まる前にお布施を渡すのが一般的となっています。
葬儀後にご遺族や親族が一堂に集まる法要・納骨式後は会食されるのが一般的です。
故人様を供養してくれた僧侶や参列者に感謝の意味を込めて、料理やお酒を振る舞いねぎらいます。生前の故人様の思い出を語り合い偲ぶ場でもあります。故人様の遺影や位牌の前にもお酒を入れた盃を用意しておきましょう。
会食の場では配膳の準備が整ったときに、施主が法要・納骨式への参列の感謝と無事終了したことのお礼をまず伝えてから挨拶をします。ご遺族の故人様への思いや近況を長くならないよう、1~2分程度にまとめます。
挨拶が終わったら献杯を行います。献杯の音頭は誰がやるとの決まりはありません。故人様と親しかった友人や親族の中でも故人様と縁の深かった方にお願いしておきます。
献杯の音頭を取る方は、自己紹介と故人様のご関係を簡潔に述べてた後に「それでは献杯をさせていただきます。ご唱和をお願いします。献杯。」と静かに発声します。
この発声により会食のスタートです。宴会ではないので乾杯したり、盃を打ち合わせたり、拍手などをせず静かな声で唱和しましょう。
会食終了の時間になったら施主は最後の挨拶をします。施主は参列者へ会食終了の時間になったことと、今後とも変わりなくお付き合いをお願いし、最後に参列のお礼を述べて終わります。
参列者に引き出物を渡して、会食は終了となります。
葬儀を終えた後は四十九日法要、百箇日法要と法事があります。この法要の際に故人様の遺骨をお墓に納める納骨式を一緒に行うご遺族が多いようです。
葬儀後に納骨式をどう行えばいいのかよく分からない。また、故人様を納骨するお墓がない場合はどうするのか、悩まれる方は大変多いです。
最近は故人様の遺骨を納骨堂に納める場合や、遺骨を海洋に散骨する、樹木・花木を墓標にした樹木葬で納骨を行う方も増えてきました。ご遺族や故人様の生前の遺志によってさまざまな納骨のスタイルがあるのは当然です。
弊社は、葬儀に関することはもちろん、葬儀後の納骨式などあらゆるご相談にも丁寧に対応しております。納骨式や納骨する場所のことでお困りのことやご不明な点がございましたらいつでもご相談ください。
花葬は、横浜市や川崎市での葬儀実績が豊富な地域の口コミNo.1の葬儀社です。口コミで3冠を達成するなど、地域の方からの信頼が厚いのが弊社です。
「もっと低価格でご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービスを提供したい」との思いで、格安でご遺族の希望に寄り添った葬儀を提供しています。公営斎場を利用し、無駄を一切省き、必要なものだけを厳選したプランとなっています。
弊社スタッフが誠心誠意を尽くし、様々な葬儀をサポートいたします。葬儀でお悩みの方はお気軽に弊社までご相談ください。
※表示価格は「資料請求割引適応後」の価格です。