川崎市の葬儀でお悩みの方へ

口コミNo.1葬儀社が
疑問を解決!
地域貢献度
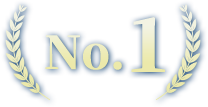
口コミ満足度
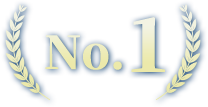
信頼と安心
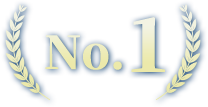
*日本経済リサーチ株式会社2022年2月期調査
川崎市の葬儀コラム|葬儀なら花葬
【目 次】
「不明瞭」な葬儀費用を適正化し
全て自社スタッフが行う葬儀社です
\ swipeスライドでもっとみる /
不安な事は何一つ無く、葬儀を迎える事が出来たのは全て…
続きを読む
葬儀において「メイク」は浸透してきましたが、「エンバーミング(Embalming)」は聞きなれない人が多いのではないでしょうか?エンバーミングは日本語訳で「遺体衛生保全」という意味になります。近年では、日本においてもエンバーミングが広がりを見せています。
今回は、エンバーミングの起源や日本での広がり、費用相場などエンバーミングを徹底ガイドします。ぜひご覧ください。
エンバーミングとは、ご遺体を衛生的に保つことができる特殊な施術の事を言います。簡単に説明すると、亡くなった方のお身体から血液を排出し、防腐液を体内に注入し衛生的に長期保管できる施術となります。エンバーミングは資格を持った専門技術者が洗浄、メイク、腐敗防止の施術といった処置を全て行います。この専門技術者をエンバーマーと言います。
エンバーミングは湯灌やメイクのように家族が立ち会う事はできず、一度ご遺体をエンバーミングセンターにお預けし施術をしてもらいます。施術の時間は体格や腐敗の状況によりますが、90分~180分となっています。
最近の葬儀は火葬場が一週間以上待つ事が多々あります。そこでエンバーミングを行う事で衛生的にもよく、綺麗な姿でお別れをする事が可能となりました。また最近ではコロナウイルスの影響でご遺族の考えも変わってきて、感染病などに敏感になりエンバーミングに興味のある方が増えてきています。
一般的な感染症はエンバーミングする事により消滅するといわれていますが、コロナウイルスが消滅するかは不明です。また交通事故死などのお体に損傷などがある場合はエンバーミングで修復し生前のお顔などに近い状態に戻す事が可能となっています。
急に残された家族の精神的な悲しみを軽減できる効果もあります。またエンバーミングをする事により、匂い・感染症なども亡くなり衛生的で自由度が増し、故人様に触れたりしながらお別れも可能です。
【一緒にお読みいただきたい記事】
北米など土葬が基本な地域では、衛生管理のための一般的な遺体処理方法としてエンバーミングが広く知られてきました。北米のほか、イギリスやシンガポールなどでも一般的な遺体処理方法となっています。
エンバーミングの起源をさかのぼると、古代エジプトのミイラまでたどり着きます。古代エジプトにおけるエンバーミングは、薬を遺体に入れることで、長期保存を可能にしていました。エンバーミングが行われるきっかけになったのは、主に以下の2つの理由からです。
・宗教的な観点から遺体の保存が必要であった
・ナイル川の氾濫で遺体が伝染病の発生原因になることを防ぐため
また、19世紀のアメリカ南北戦争では、兵士の遺体を故郷まで輸送する際に、エンバーミングが施されていたという記録があります。
衛生面の良化や遺体の状態回復、消臭などを目的に遺族の元にご遺体を帰す際の手段として用いられていたのです。その後、ベトナム戦争でもエンバーミングは行われていました。
エンバーミングは、古代エジプトからナイル川氾濫による伝染病、アメリカ南北戦争などの歴史を経て技術を向上し、現在に至るのです。
日本におけるエンバーミング初の実施例は、1988年です。同年には、エンバーミングセンターが日本で初めて開設されました。
最初は、外国人のエンバーマーによって処置が行われていました。それからアメリカに渡り、専門的な技術を学ぶことで「エンバーマー」の資格を取得する技術者が日本でも徐々に増えてきたのです。
現在の日本では、IFSA(日本遺体衛生保全協会)が基準を設け、技術者の育成、指導を積極的に行っています。
尚、エンバーミングの処置方法である小切開は、刑法190条「死体損壊罪」に抵触しないという法的解釈にもとづいて実施されています。
日本でのエンバーミングは、当初、火葬率ほぼ100%の日本で必要なのかと度々議論されていた話題です。しかし、1995年の阪神淡路大震災では、多くの犠牲になられた方々にエンバーミングが施されたことをきっかけに、一般にも広く認知されるようになったのです。
エンバーミングは、ご遺族や親しかった人々の大きな慰めとなり、ご遺体を綺麗な状態で保つ技術として、現在では多くの場所で取り入れられています。
エンバーミングは大手の葬儀社が自社でエンバーミングセンターを保有しています。また現在ではエンバーミングの専門学校(日本ヒューマンライフセレモニー)まで平塚で開校されています。
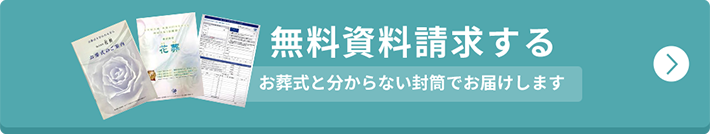
1)まずは故人様の衣服を脱衣し、身体の状態を確認します。
2)お身体の洗浄、消毒を行います。
3)首と太ももの血管部分を切開し、血液を排出します。切開については衣服で見えな
4)胸部、腹部から貯留した水分(腹水など)、老廃物を除去します。
5)血液の排出・老廃物などがなくなりましたら薬品を体内に注入します。エンバーの専用の機器で薬品が体内に循環するようにマッサージなどをしながら執り行います
6)切開箇所の縫合などをして再度、身体の洗浄
7)ご遺族の用意した洋服・仏衣などに着替えます
8)最後に髪型などを整えてお化粧をして終了
エンバーミングの基本料金は、15万~25万円程度です。ご遺体の損傷が大きい場合には、修復のために特殊技術などを用いることもあります。こういったケースでは、10万円程度金額が加算されることも多くなっています。
尚、基本料金には、ご遺体の搬送費や棺の費用、衣装費などが含まれないことがほとんどです。ご遺族は、基本料金にプラスしてこれらの費用が必要になることを予め理解しておくとよいでしょう。
尚、エンバーミングは、生前のご本人、または、家族(二親等以内の反対がない場合)によって申し込みができます。
エンバーミングは、これまでに多くの著名人が行っています。以下に、エンバーミングを施した著名人を紹介しています。著名人は、弔問に多くの人が訪れることなどの理由から、ご遺体を綺麗な状態で保存したいと思い、希望されるケースも多くなっているのです。
・ホー・チ・ミン(ベトナム革命家)
・毛沢東(中国の政治家)
・金正日(北朝鮮の指導者)
・マイケル・ジャクソン(アメリカ合衆国のシンガー)
・マリリン・モンロー(アメリカ合衆国のモデル、女優)
・テレサテン(台湾出身の歌手)
・エイブラハム・リンカーン(第16代アメリカ合衆国大統領)
いかがでしたでしょうか? ご遺体の皮膚の状態は、生存中とは全く異なるものであり、腐敗は免れないことです。エンバーミングを施すことで、ご遺体の長期保存が可能になります。
日本では、闘病生活が長い場合や事故などによる損傷が大きい場合などにエンバーミングがよく用いられています。できるだけご遺体を綺麗な状態で見送りたいと考え、エンバーミングを選択されるご遺族が増えているのです。
川崎市ではダビアス・横浜市メモワールなどが積極的にエンバーミングのセンターを保有し積極的に施術しています。弊社でもエンバーミングの手配はかのうですのでご相談ください。
横浜市や川崎市の葬儀には、ぜひ弊社をご利用ください。弊社は、業界最安値を実施している地域密着型の葬儀社です。地域の特徴やしきたりを理解し、地域のお客様から厚い信頼があります。
葬儀にお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。弊社スタッフがご要望をお伺いし、ご希望の葬儀を実現いたします。

㈱花葬は、現代表の大屋徹朗(※平成21年9月30日に「葬祭ディレクター1級」を取得)が、大手葬儀社の営業時代に感じた『もっと低価格でご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービスを提供したい』との思いから、2017年に川崎市中原区で創業した葬儀社です。2021年10月で創業5年目を迎えますが、2021年5月末現在、横浜市・川崎市で既に1.500件以上の葬儀提供実績があり、おかげ様で多数のメディアでも取り上げられております。
現在、川崎フロンターレの公式スポンサーを務めており、両者と地域貢献活動でも連携を取っております。その取り組みが評価され、2020年、2021年に社会貢献が川崎市より評価され、表彰を受けました。また、2021年より「SDG.S 川崎市ゴールドパートナー」としても認定されています。
弊社では、可能な限りお客様のご要望を叶えるための柔軟な葬儀プランと併せて、川崎市の公営斎場(かわさき南部斎苑、かわさき北部斎苑)と横浜市の公営斎場(横浜市戸塚斎場、横浜市久保山霊堂、横浜市南部斎場、浜市北部斎場)を利用することで、出来るだけ葬儀費用を安くするご提案を実施しております。
お陰様で、弊社はご利用いただいた皆様からの評価が非常に高く、「ご紹介」や「リピート」でのご依頼が半数を占めます。これからも『ご遺族の気持ちに寄り添ったご葬儀サービス』をモットーに、高品質な葬儀サービスのご提供に努めて参ります。
運営会社:株式会社花葬
川崎フロンターレ・川崎ブレイブサンダース 公式スポンサー
※表示価格は「資料請求割引適応後」の価格です。