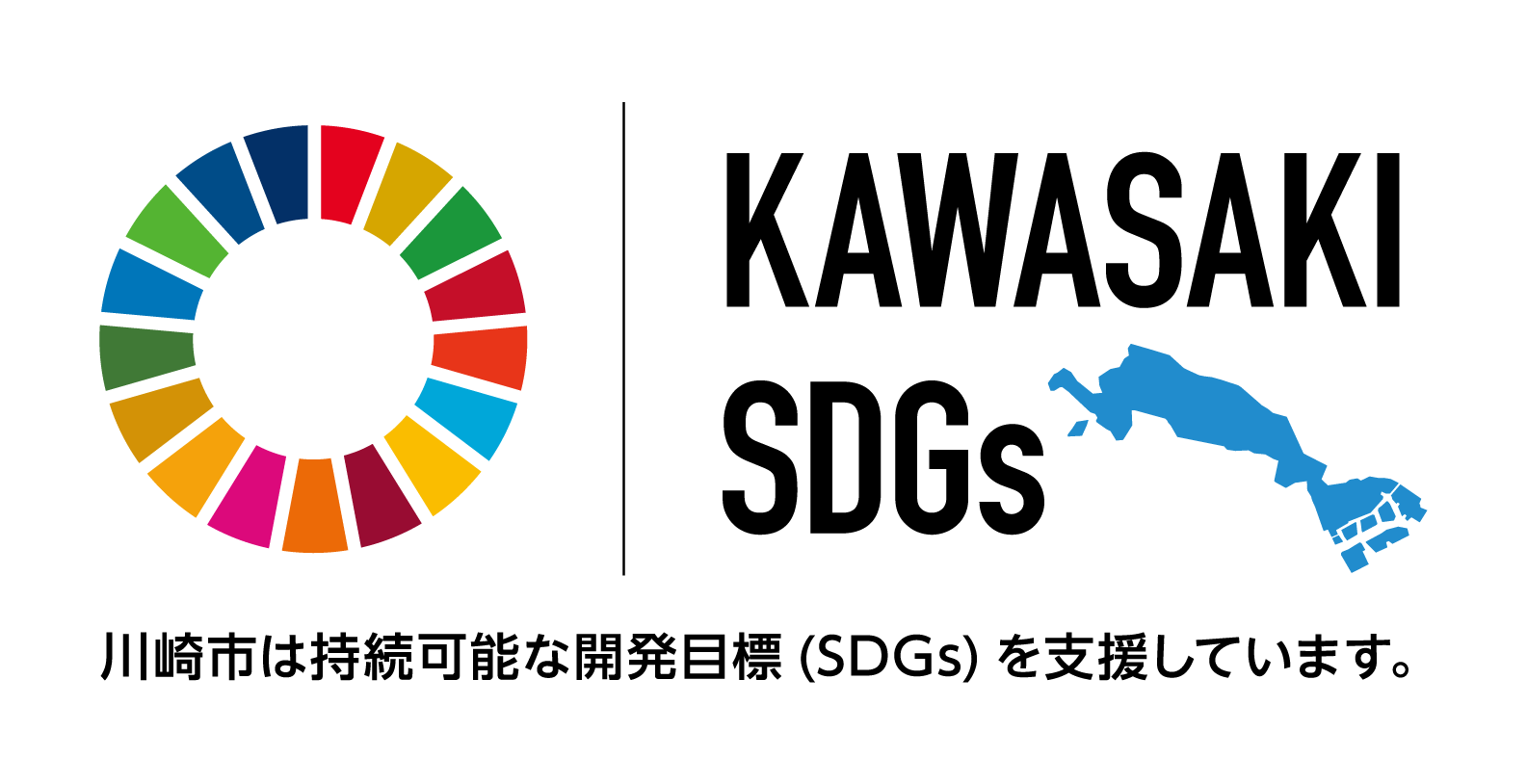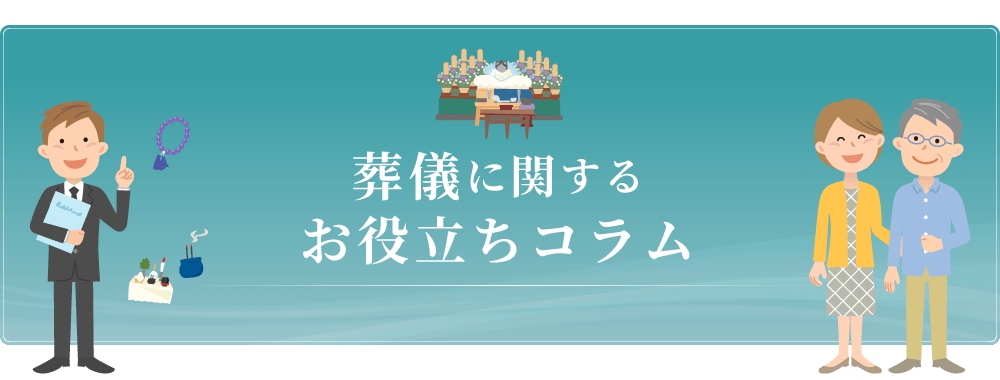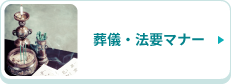2020/06/30
葬儀とは何か 一般的な葬儀の流れ(臨終から通夜まで)
今回は「一般的な葬儀の流れ」に関するお話を掲載します。葬儀とは、臨終からご遺体の火葬、死後の供養までの一連の「葬送儀礼」のことを指します。お葬式とは参列者が故人とお別れをする「告別式(葬送儀礼の一部)」を指すのが一般的です。
葬儀の流れは、【臨終⇒搬送⇒安置⇒納棺⇒通夜⇒告別式⇒出棺⇒火葬】が一般的です。地域によっては火葬のあとに告別式(骨葬)を行うこともあります。直葬、家族葬、密葬など葬儀の形式はありますが、今回は一般的な葬儀の流れ(通夜まで)をご紹介していきます。